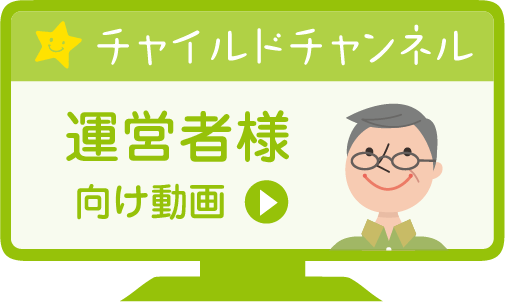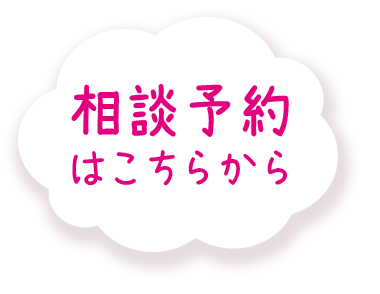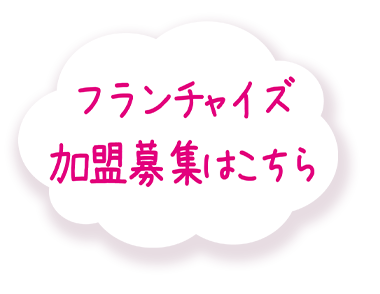1日の流れ
-
★順次各学校へお迎え
14:30 ~
? 子ども達の様子を確認します
? 今日の予定を話し合い、確認します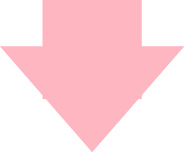
-
★療育運動、
集団遊び15:00
? 自分で選択し楽しむことを大切にします
? 子ども達の発達のサポートをします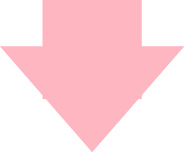
-
★おやつ
16:30
? 必要に応じておやつや休憩をします
? 脳の活性に必要な「水を飲む」ことには気をつけています
? おやつの時間は仲間を作るきっかけとしています
(はじめは個別支援ですが集団活動の入り口となる時間です)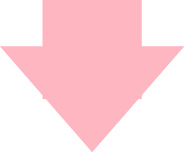
-
★宿題、工作、
お絵描き等16:45
? 学校の宿題を中心に行います
? 保護者の方からリクエストがあれば、それも取り組みます
? 認知力・理解力・戻り学習等のために取り組みます
(プリントを作りサポート)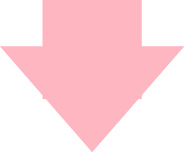
-
★帰りの会
17:45
? 子ども達の「できた」「良かった」を分かち合います。
? 感情の折り合いをつけ、
家庭や学校で楽しくすごせるように後押しします。 ※送迎スケジュールにつきましては個別にご相談ください。
対応・検討させていただきます。
(土、祝日 / 10:00 ~ 16:00)


土曜日は外出イベント等を行っています。(※毎週ではありません)室内ではできない動きができるトランポリン施設、体育館、大きな公園等に出かけ、身体を沢山動かしたり、社会見学へ行ったり、体験したり、工作や調理イベント、動物の触れ合いや、音楽体験など、子どもたちと相談して、イベント行事を行っています。なお、イベント等がない土曜は、月曜から金曜の日の流れに沿います。
遊びを「勉強するためのごほうび」、
「いい子にしていたら遊んでも良いよ」と、
考えていません。
「学習の集中力をつける」「より良い目の使い方ができるようになる」「コミュニケーションをさらにスムーズにする」などの、狙いを持って「療育運動、集団遊び」をした後に学習する、という1日の流れです。
チャイルドハートの取り組み
-
運動トレーニング
思いきり身体を動かし、楽しみます
遊びを通して身体を自然に動かし、その中に発達のポイントを観察します。そして、お子さんの自発的な遊びや発達につながる的を得た遊びを提供します。呼吸・感覚・動き・姿勢を整える遊びを通して、人しかできない言葉を話すことや、コミュニケーション、学習、認知、記憶、理解、細かな微細運動などの高度なことを自然と行える身体になるよう、満足するまで体を使い切ります。動きのないお子さんも動くだけが運動ではないので、一人ひとりにあった発達につながる遊びを沢山行うことができます。表面部分の補い運動ではなく、“できない”の原因の基礎からやり直す遊びをしていきますので、強固な基礎が作られてくると、今までどんなに頑張ってもできなかったことが、自然と頑張らなくても普通にできるようになります。これが、基礎強化による発達の原理です。

-
学習支援
個々のペースに合わせた環境で学びます
まずは宿題のお手伝いからスタートします。発達の 凸 凹 のお子さんは、ビジョン(視覚)から得る情報が正確な情報として取り入れられていないことがほとんどです。学習支援はまず、身体を通してビジョン(目)の発達を促します。プリントを使った認知トレーニング、理解力のトレーニング、戻り学習の勉強等の方法も活用しますが、基本的な身体や目の使い方が大変なうちは、学習などの目で見たり、手を使って書くなどの作業がお子さんたちにとっての大きな負担となる為、時期を見て学習の提案をさせて頂いています。

-
ソーシャルスキルトレーニング
お友達と一緒にいろいろなことにチャレンジします
ソーシャルスキルトレーニングでは、10人定員という少人数ならではの手厚い関わりの中で、挨拶からお片付け、お友達とのコミュニケーションなど、学校生活や社会等に出た時、困ることが少なくなるよう支援させて頂いています。お子さんたちはチャイルドの中で、必ず“友達”とゆう大切な仲間を持ちます。お友達とのやり取りの中で子供同士でしか学べない社会性、会話の間合いや、感情のやり取りを通して、親御さんや先生からでは学べないことを沢山学びます。将来【自立】して生きていける為の術を沢山学びます。

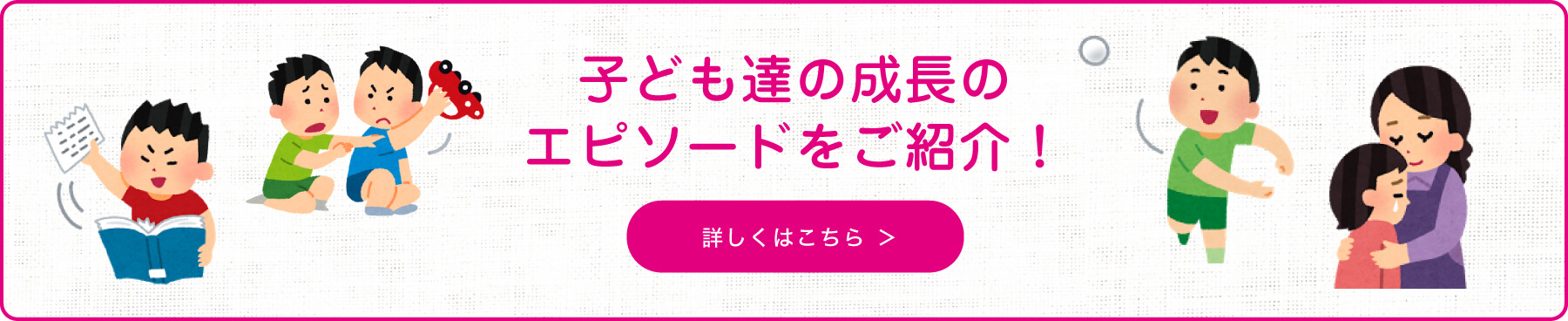
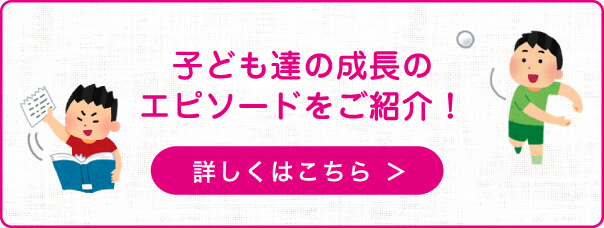
保護者の方にお願いしたいこと
-
1.子ども達の「できない」だけでなく、「出来るようになったこと」「素晴しいこと」
に焦点を当てた会話をさせてください。子ども達の「自己肯定感」を育てるためには、周囲の「認める力」が必要です。子ども達が何か出来るようになると「もっと出来たらいいのに」と、要求のハードルをすぐあげてしまいがちですが、少し立ち止まって「出来るようになったこと」「素晴しいこと」に目を向けた会話をしませんか?そして、子ども達の成長を、子ども達とともに喜び合いたいと思います。
-
2.発達支援講座・ママ会などへご参加ください(できる範囲でけっこうです。)
毎日忙しいことは、私たちも充分理解しています。でも、できる範囲で発達支援講座・ママ会にご参加ください。お互いに率直に話し合える場がたくさんあることが保護者と職員の信頼を作ると考えています。「こんなこと言ってもいいのかなあ...」と、思うような些細な「気がかり」「不安」「アイディア」もお話ください。私たち職員には耳が痛いこともあるかもしれませんが、できる限り受け止め改善して行きたいと思います。また、特技がある保護者の方はご自身が先生になってください。子ども、職員、保護者の成長に共感してくださる勉強会の先生をご紹介ください。「けん玉」「楽器演奏」「おもちゃ作り」などたくさんの保護者・支援者の先生がいます。講師謝金は、とても少しですが、弊社規定に沿ってお渡ししています。)